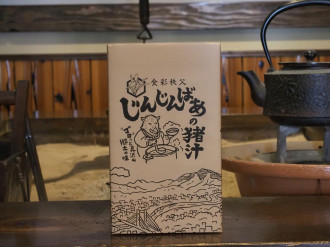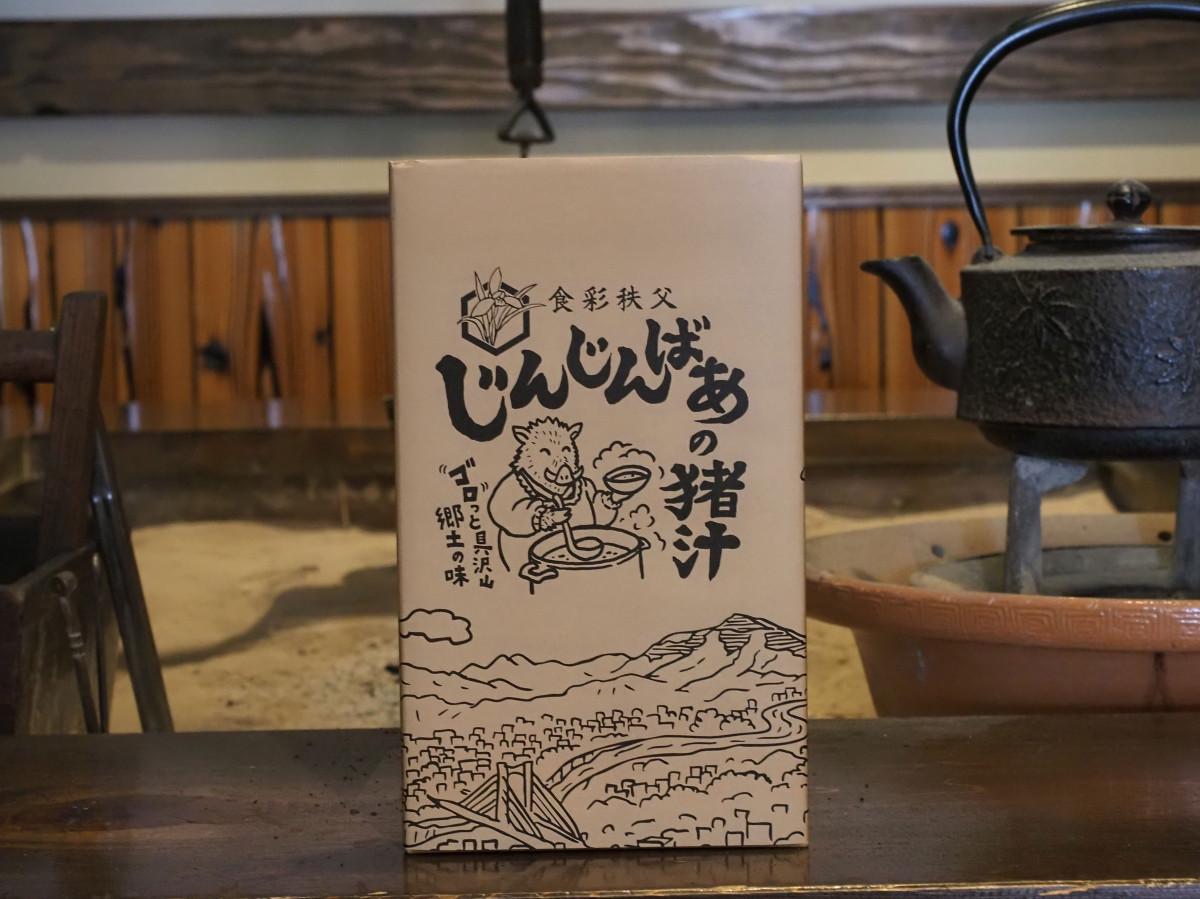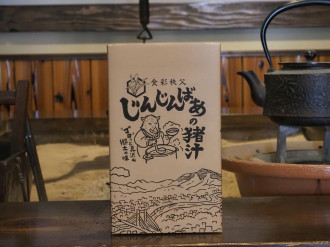「歴史ロマン」をテーマにした体験型ツアー「盃状穴(はいじょうけつ)探索会~誰も知らない古代秩父の歩き方~」が11月19日・20日、秩父エリアで開催された。都内や九州からの参加者も含め、2日間で延べ51人が参加した。
講師を務めた武内さんは、国内外の巨石文化の研究・保全活動に取り組んでいる
主催は秩父地域の盃状穴の調査や研究を行う市民団体「秩父歴史ロマン研究会」(横瀬町横瀬)。ツアーでは盃状穴に関する基礎講座、研究者・地元の案内人によるフィールドワーク、参加者同士のディスカッションが行われた。
盃状穴とは、岩盤に直径数センチの小さな穴が複数開けられた遺構(いこう)。縄文~近世にかけて作られたと考えられており、全国に分布している。「信仰儀礼」「安産祈願」「天体観測」「雨乞い」など多様な説が存在するものの、目的や用途は明確には解明されていない。
講師を務めた武内一忠さんは、国内外の巨石文化の研究・保全活動に取り組んでいる「守ろう・巨石文化と森と水」の代表を務める。文化財としては認定されていない巨石文化の歴史的価値の研究や保全のため、講演会やツアーを開催している。
武内さんは「秩父地域では盃状穴は他地域よりも多く存在している。秩父は、東京を支える荒川の源流域で『関東の水がめ』として極めて重要な場所。秩父の札所が始まったのには弘法大師が深く関わっており、弘法大師は水が豊かな場所に寺院を建てたといわれる。そうした水と信仰の結びつきの強い土地に、多く盃状穴が存在しているのは興味深い」と話す。
ツアーを企画したのは、横瀬町のゲストハウスに長期滞在している滝口峻平さん。歴史文化に関心があり、盃状穴を知って世の中に知られていない文化があることに心を引かれた。盃状穴について調べるようになり、今年、「秩父歴史ロマン研究会」を立ち上げた。
参加者からは「関東では希少な盃状穴を多く見ることができた」「秩父が荒川の源流域であり、地形を教えてもらえたことが勉強になった」「以前訪れた神社でも、その時には気づかなかった重要な井戸や盃状穴を発見することができた」などの声が聞かれた。
滝口さんは「今後も秩父地域での盃状穴の探索を進めていきたい」と意気込む。