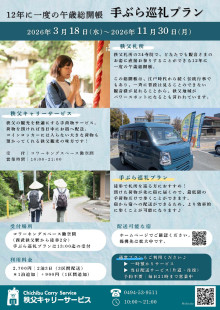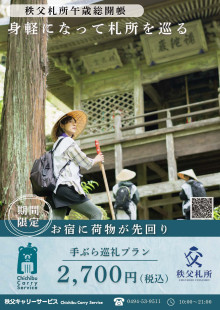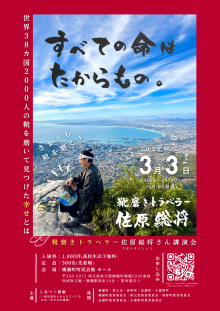「秩父地域と自伐型林業」をテーマとしたフォーラムが8月24日、秩父市歴史文化伝承館・研修室で行われる。主催はNPO法人「自伐型林業推進協会」で、全国的な動向や秩父地域での取り組み、近隣地域の事例紹介などを通じ、小規模・自立的な林業の可能性を探る。
倒木の技術だけでなく、「どう倒すか」「切ったらどうなるか」をじっくり考える
自伐型林業とは、山主や地域住民が自ら木を切り出しながら森を育てる林業。「良木を残して山の価値を高め、自然の力と調和しながら収益も得られる新しいなりわいの形」だという。担い手を育てる研修は、この10年間で全国で延べ1万人ほどが参加しており、秩父地域では4年ほど前に取り組みが始まった。
秩父地域は山林面積が広い一方で急傾斜地が多く、大型機械が入りづらい現場も少なくない。これまでの体験研修への参加は約50人。市の支援制度を活用しながら自伐型林業を始めた新規参入者は10人ほどに上る。移住者や他業種と兼業する若者など、多様な背景を持つ人々が担い手として現れ始めているという。
今回のフォーラムでは、自伐型林業推進協会の上垣喜寛事務局長が全国的な動向の紹介に加え、秩父地域や近隣の小川町での具体的な先行事例も報告する。同市の現役の地域おこし協力隊員や卒業した隊員も登壇し、現場の実情や可能性について意見交換や質疑応答の時間も設ける。
上垣さんは「秩父にはまだ多くの手つかずの山林がある。大規模事業体に任せるだけではなく、地域に根ざした人々が少しずつ森を育てていく仕組みも必要。今回紹介するのは、新たに担い手として歩み始めた人たちで、山主の皆さんと共に森を未来へ引き継ぐ関係を築いていけるような機会にしたい」と参加を呼びかける。
開催時間は13時~15時。参加無料。事前申し込みは8月22日まで受け付ける。